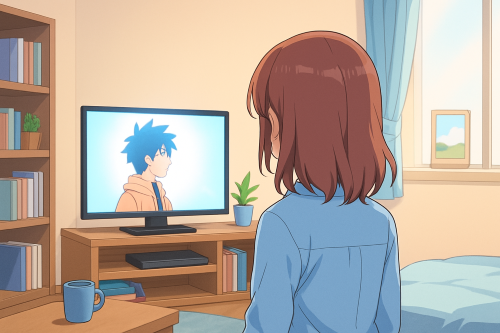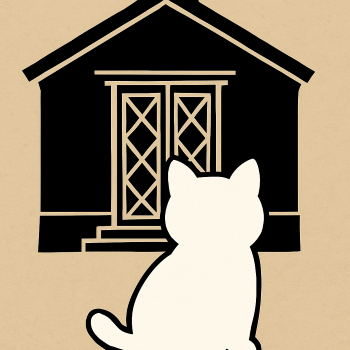その選択は本当に自分の意思で決めているの?

私たちは、日々無数の選択をしています。しかし、その選択は本当に自分の意思で決めているのでしょうか? シーナ・アイエンガーの著書『選択の科学』は、選択の背後にある心理や社会の影響を解き明かし、私たちが思っているほど自由に選んでいないことを示唆します。本書を読むことで、より良い選択をするための洞察が得られます。
コロンビア大学教授:シーナ・アイエンガー
シーナ・アイエンガーは、コロンビア大学の教授であり、選択のメカニズムを研究する第一人者です。彼女は視覚障害を持ちながらも、自らの選択と環境がどのように意思決定に影響を与えるのかを探求してきました。本書では、
・選択肢が多すぎると逆に選べなくなる「ジャムの法則」
・文化によって選択の意味が異なること
・実は選択の多くが社会や環境に左右されていること
といった、驚くべき研究結果を紹介しています。私たちが自由に選んでいると思っていても、実際には多くの要因に影響を受けているのです。
例えば、スーパーマーケットで24種類のジャムを試食できるコーナーと、6種類のジャムだけを試食できるコーナーを用意した実験があります。一見、多くの選択肢があった方が購買につながりそうですが、実際には6種類のコーナーの方が購入率が高かったのです。これは「選択肢が多すぎると迷いが生じ、決断が難しくなる」という心理的な傾向を示しています。
また、日本とアメリカの子どもを対象にした研究では、親や先生が選んだ課題に対して、日本の子どもは意欲的に取り組み、アメリカの子どもは興味を失ってしまうという結果が出ました。これは、文化によって「誰が選ぶのか」という要素が、モチベーションに大きく影響することを示唆しています。かなり興味深いですよね。
実は結構、選択する際、多くの制約や影響化にある
私たちは選択を通じて自由を実感したいと願いますが、実際には多くの制約や影響を受けています。本書を読むことで、自分がどのような環境で選択しているのかを理解し、よりよい意思決定をするヒントを得ることができます。
『選択の科学』は、日常のあらゆる場面で役立つ一冊です。もし、「本当に自分の意思で選んでいるのか?」という疑問を持ったことがあるなら、ぜひ、読んでみてください。

選択の科学 コロンビア大学ビジネススクール特別講義 (文春文庫 S 13-1)